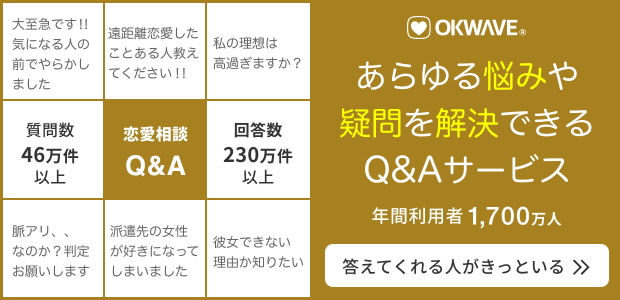「終活」と聞くと、遺言書やお墓の準備、財産の整理などをイメージする人が多いかもしれませんが、今の時代だからこそ忘れてはならないものがあります。それは、デジタル資産の存在。
スマホやパソコン、SNS、ネット銀行など、目に見えないデジタル資産をどう扱うかは、特に40代・50代のおひとりさまにとって重要な課題です。「やっておくと安心」ではなく「やっておくべき」と捉えた方が良いでしょう。
この記事では、おひとりさまだからこそ備えておきたい「デジタル終活」の基本と、頼れるような人が誰もいない場合の実践的なヒントをお伝えしていきます。
「デジタル終活」って何?
「デジタル終活」とは、スマホやパソコン、クラウド上にある情報を整理し、家族や信頼できる人に伝えられるよう準備をしておくことを指します。たとえば、以下のようなデジタル資産が対象になります。
●スマホのロック解除情報(パスワード、生体認証)
●メールやSNSのアカウント
●ネット銀行・証券口座・キャッシュレス決済
●サブスク契約(動画、音楽、ゲーム、各種アプリなど)
●クラウド上の写真や文書、パスワード管理アプリ
●スマホに残された連絡先や日記、メモ
これらはアナログ資産とは異なり目に見えるものではありません。スマホやパソコンにロックがかかっていれば、たとえ家族でも中を見られず対応がとても困難になります。
デジタル終活をしない場合のリスク
デジタル終活をしておかないと、自分に万一のことがあった際に次のようなトラブルが起こる可能性があります。
●銀行や証券口座の存在に家族が気づかない
●サブスクなど各種料金の支払いが延々と続いてしまう
●SNSにアカウントが残り続け、誤解や混乱を生む
●大切な写真やデータが取り出せないまま消失する
「遺影に使う写真が取り出せない」「ネット銀行の口座が凍結されたまま」「サブスク料金が引き落とされているのに、会員IDが分からず退会できない」など、家族を亡くした人の間でこうしたトラブルは増える一方。
実際に、国民生活センターにもデジタル遺産関連のトラブルに関して多数の相談が寄せられている状況です。
「おひとりさま」の場合はこれらを頼める相手が限定されているからこそ、自分の手で「信頼できる誰かに伝える」仕組みを準備しておくことがとても重要です。
自分が元気なうちに「何を残すのか」「何を消すのか」「誰に託すのか」を決めておくことがこれからの時代の終活です。
スマホの中身を3つに分類して考えよう
デジタル終活の重要性は分かっていても、いざ取り組むとなると何から始めて良いか分からない人も多いでしょう。ここでは、具体的な進め方についてアドバイスをしていきます。
まずはスマホやパソコン内の情報を次の3つに分類することからはじめましょう。
財産に関わる情報
ネット銀行、証券口座、電子マネー、保険、サブスク契約など。改めて整理をしてみると、財産に関わるアプリってたくさんインストールされていますよね。特に有料サービスの解約忘れは、残された人の金銭的負担になりやすいので注意が必要です。
人とのつながり
連絡先(電話番号やメールアドレス)、LINE 、SNSなど。急な訃報の際、連絡すべき人や方法を誰かが知っている状態にしておきましょう。
思い出やプライベート
写真、日記、メモ帳アプリ、画像や動画、LINEのログ、検索履歴など。「見て欲しいもの」「見てもらっても問題ないもの」「絶対に見られたくない!恥ずかしいもの」を取捨選択しておきましょう。
おひとりさまが始めるデジタル終活の手順
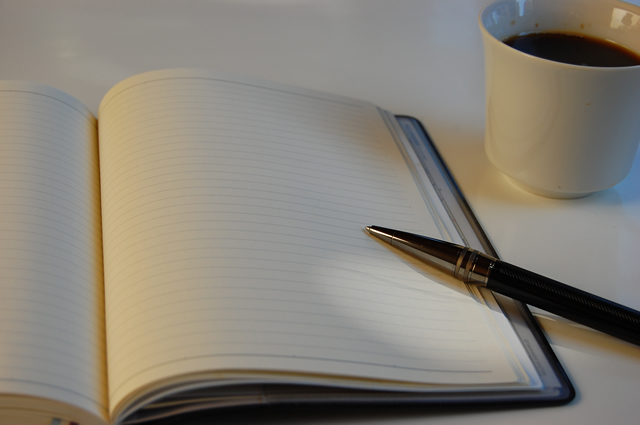
デジタル終活に初めて取り組む人は、下記のステップで少しずつ始めましょう。
ステップ1:情報を書き出す
エンディングノートや終活アプリなどを利用して、最低限、下記の情報をまとめておくのが理想です。
●使用中のアカウント一覧(SNS、金融、ショッピングなど)
●サブスク契約や有料アプリ
●よく連絡する人のリスト
●見られたくないデータ(削除したいもの)
紙に書きだしておきたい場合は、エンディングノートを利用しましょう。無料テンプレートが多数配布されていますし、ダイソーなど100均にもあるので手軽に手に入ります。すべての情報をスマホで完結させたい人は、終活向けのアプリがおすすめです。
エンディングノートのテンプレート(法務局)
我が家ノート-アプリで始める終活の第一歩-
SouSou
ステップ2:パスワードの扱いを決める
すべてのID・パスワードを記録するのは現実的ではないため、「重要なものだけメモする」「パスワード管理アプリを活用する」「別紙に書いて封筒で保管する」など、自分に合った方法を選びましょう。
ステップ3:残すか消すかの判断をする
例えば、
●旅行の写真 → 残す
●恋人とのLINE → 消す
●仕事のファイル → 整理して残す
●一般的な趣味のデータ → 残す
●見られたくない趣味のデータ → 消す
といったように、カテゴリごとに「残したいもの&消したいもの」を整理します。いくら自分の死後だからといっても、見られたくないものは見られたくないものですよね。
誰に託すかで変わるデジタル終活の準備
デジタル終活では「まとめた情報をどこに残しておくか」だけでなく、「誰に伝えるか」が重要です。特に独身で身寄りが少ない人や、家族との関係性が良くない場合「誰かに託す」こと自体がハードルになる場合もあります。
ここでは、「託せる相手がいる場合」「いない場合」それぞれに合わせた方法、そして情報を託す際の注意点を解説します。
1. 託せる相手がいる場合(子ども、兄弟姉妹、親しい友人など)
信頼できる人がいる場合は、その人に最低限の情報だけでも託しておけると心強いです。
●子ども(成人していて信頼できる)
●兄弟姉妹(仲が良く、生活背景を理解している)
●長年の友人(家族よりも気軽に頼めることも)
伝え方のポイント
相手の同意を得る:「もしものときお願いしてもいいかな?」と軽く相談しておくことで双方の安心感が生まれます。
伝える情報は分けてもいい:すべての情報をひとりに託す必要はありません。たとえば「金融情報は子どもに」「SNSやスマホ内の写真などは友人に」などと情報を分散化しておくのもひとつの方法です。
情報の受け渡しは「まだ見られたくない」気持ちも考慮して:
●封筒に入れて「今は開けないでね」と預ける
●暗号化したUSBに入れてパスワードだけ伝える
など、プライバシーを守りながら託す方法もあります。
2. 託す相手がいない場合(完全におひとりさま)
一方「身近に託せる人がいない」場合はどうすればよいのでしょう。今は「公的・民間のサポート」「書面での自己管理」など、完全におひとりさまの場合でも実行できる方法が整ってきています。
専門家に委任する
「死後事務委任契約」を結び、行政書士・司法書士などにデジタル資産の整理を依頼することができます。費用はかかりますが法的にしっかり対応してくれる安心感があります。相続などが絡む場合も心強い存在です。
エンディングサービスを活用する
近年は、以下のようなオンラインサービスも注目されています:
●死後にメッセージや情報を送信する「デジタル遺言」
lastmessage(ラストメッセージ)
SMBCデジタルセーフティーボックス
●一定期間アクセスがなければ通知が届く「見守り機能付きエンディングノート」
Memory Container™
つなまも
パスワード管理アプリの継承設定
中には無料で使えるものもあるので、まずは試してみるのもおすすめです。
自宅に残すという方法もある
●情報を印刷・記入した「デジタル終活ノート」を作り、自宅のわかりやすい場所(仏壇・引き出しなど)に保管する
●封筒に「万一の際に確認してください」とメモを添えておく
たとえ誰にも渡さなくても、「いざというときに誰かが気づける工夫」をしておくだけで、周囲の負担は大きく減ります。
3.託せるパートナーを探す
終活婚という言葉があるように、終活を見据えた信頼できるパートナーを探す方法もあります。20代~30代のマッチングアプリでは「婚活=法律婚」一択でも、40代を過ぎれば事情が変わります。法律婚は考えていない人も、終活を念頭に置いた「信頼できるパートナー」を見つけておくのもひとつの方法です。
ただし、一般的な婚活向けのマッチングアプリの場合は法律婚を望んで利用する人が大半なので、利用者の対象年齢や結婚に対する考え方がマッチするサービスに登録することが大切です。
情報を託すときの3つの注意点
定期的な更新を忘れずに
アカウントやパスワードは変わりやすいため、半年に一度は見直しましょう。
相手に過度な負担をかけない
いくら親しい相手でも、急に大量の情報を渡すと相手が負担に感じてしまいます。伝える情報は「必要最低限」から始めて、少しずつ共有する形でも構いません。
「見せたくないもの」の扱いを考える
たとえば日記や過去のメッセージ、創作物など、見られたくないデータは消去するか、別フォルダに分けて保管。「死後に自動削除されるアプリ」を使うのもひとつの手です。
40代50代のおひとりさまだからこそ「今」備える
単身世帯が増える今、デジタル終活は避けて通れません。
おひとりさまだからこそ「誰かが困らない準備」をしておくことが大切です。自分のスマホやパソコンを未来の誰かの目線で見直し、今日から始めてみましょう。